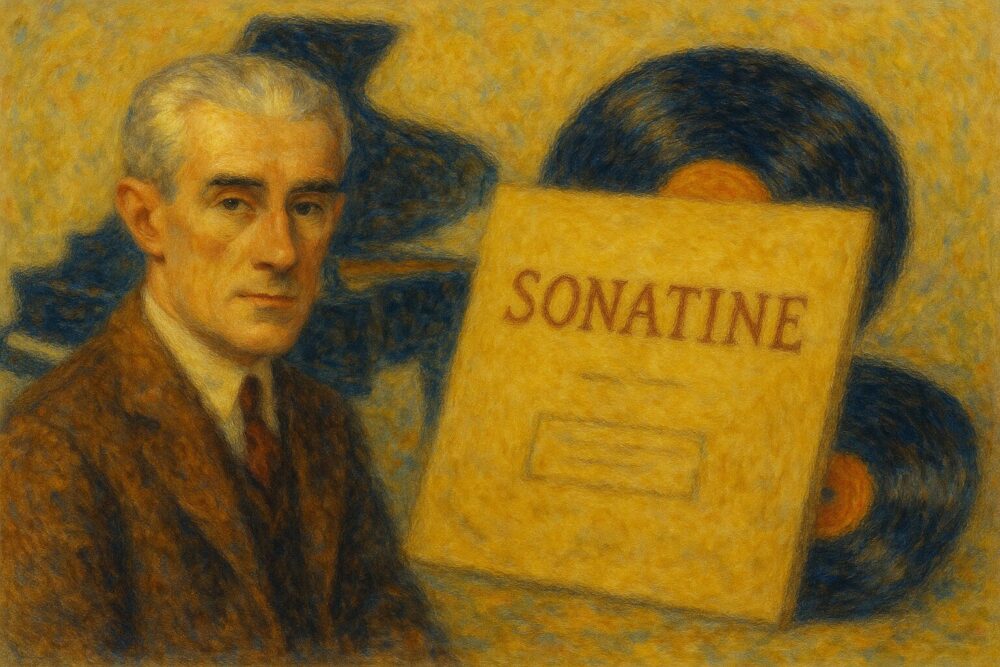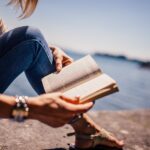こんにちは。

と、こういった方のお役に立つようにまとめました。
この記事の構成などは「もくじ」に👇
ラヴェルのソナチネ。サクッと解説
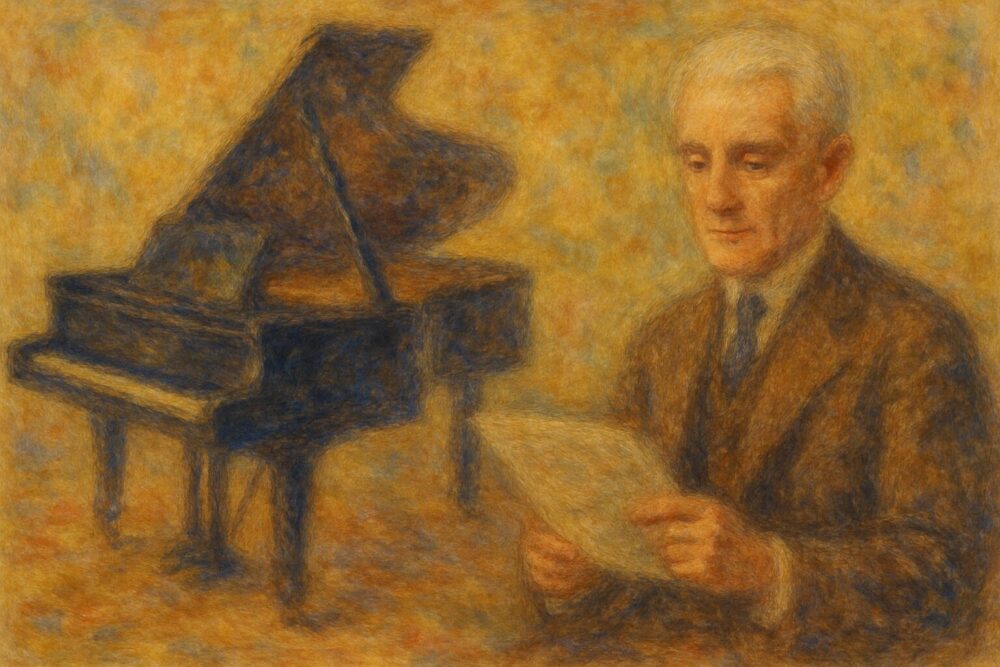
ラヴェル《ソナチネ》の概要を
| 作曲年 | 1905年(ラヴェル31歳) |
| ジャンル | ピアノ独奏曲 |
| 背景 | 作曲コンクール用(75小節以内の制限あり) |
| 特徴 | 精緻な和声、旋律美、古典的な形式美が融合 |
| 評価 | 小規模ながら完成度が高く、代表作の一つ |
各楽章の特徴まとめ
| 楽章 | 形式・特徴 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 第1楽章 Modéré(中庸の速さで) |
ソナタ形式(提示・展開・再現) | 4度下降の動機が循環 和声が色彩的で繊細 |
| 第2楽章 Menuet(メヌエット) |
トリオなしのメヌエット形式 | 優美な旋律、美しい和声 終結部は「踊りのあとのお辞儀」 |
| 第3楽章 Animé(生き生きと) |
無窮動風のトッカータ 自由なロンド形式またはロンド・ソナタ形式 |
スピード感ある音楽 第1楽章主題が再登場し統一感あり |
構成と演奏のポイント
- 古典的な構成に、ラヴェル独自の響きが融合
- 動機が各楽章に循環し、全体に統一感がある
- 細やかな表現力やレガートの技術が求められる
この曲を学ぶ魅力
- 親しみやすく演奏効果も高い
- 和声や構成を学ぶ教材としても優秀
- ラヴェルの世界観に触れる第一歩としておすすめ
ラヴェルのソナチネの難易度は?

ラヴェルの《ソナチネ》は、「ソナタより易しい小品」と誤解されがちだけど、実際は「小規模なソナタ」という意味で、初級者向けの簡単な曲ではないです。全3楽章からなり、ラヴェル独自の精緻な書法と美しい響きが詰まった作品。
各楽章の難易度と特徴
| 楽章 | 難易度 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 第1楽章 | やや高め(中上級) | ソナタ形式。両手の重なりや独特な和声進行で譜読みが難しいと感じることも。手が小さい人は無理な力が入りやすく注意。 |
| 第2楽章 | 中級〜中上級 | メヌエット風でテンポはゆっくり。譜面は短く取り組みやすいが、響きの美しさや音のバランス、表現力が重要。単純な「易しさ」とは異なり奥深い。 |
| 第3楽章 | 上級 | テンポが速く技巧的。3楽章の中で最も難易度が高く、多くの演奏者が苦戦するポイント。 |
総合的な難易度評価
- ラヴェルのピアノ作品の中では比較的取り組みやすい部類。
- 第2楽章は「ラヴェルを弾いてみたい」中級者が最初に選ぶことも多い。
- 表現力や和声感覚が必要で、音楽的な成熟が求められる。
- 第3楽章は技巧的な難所が多く、上級者向け。
参考:他のピアノ曲との比較
- 「エリーゼのために」「アラベスク第1番」などと比べると、譜読みや響きのコントロールが難しく感じられる。
- 「水の戯れ」「道化師の朝」などのラヴェル大曲よりは取り組みやすいが、十分な基礎力と表現力が必要。
難易度の「まとめ」を
ラヴェルの《ソナチネ》は、見た目やタイトルの印象よりも難易度が高く、中級者以上向けの作品です。特に第3楽章は上級者向けで、全体を通してラヴェル特有の響きや繊細な表現が求められます。譜読みやテクニックだけでなく、音楽性を磨くための優れた教材として、多くのピアニストに愛されています。
ラヴェルのソナチネのオススメ楽譜

オススメは2つで結論、デュラン版とペルルミュテール版。個人的にはペルルミュテール版がイチオシ!
デュラン版(Durand)
- 特徴
ラヴェルが存命中から出版されていた最も伝統的な原典版。フランスのデュラン社によるもので、作曲者の意図に近いとされている。 - メリット
- 原典に忠実な譜面で、国際的な標準版
- 日本語ライセンス版(ヤマハ)もあり、国内で入手しやすい
- デメリット
- 運指や解説が少なく、初学者にはやや不親切
- 価格がやや高め。欧州版は製本の質にばらつきがある
- 入手情報
ヤマハミュージックより日本語ライセンス版が発売されており、国内で簡単に購入可能。
- ラヴェル「ソナチネ」デュラン版(Amazon)
- ラヴェル「ソナチネ」デュラン版(楽天市場)
音楽之友社版(ペルルミュテール校訂)*オススメ!
- 特徴
ラヴェルの最後の弟子であるペルルミュテールによる校訂版。演奏のヒントや直伝の解釈が豊富。 - メリット
- 校訂者による書き込みが多く、直感的で分かりやすい
- 演奏解釈を深めたい人、研究用として最適
- デメリット
- 譜面がやや煩雑に感じられることもある
- 原典主義の人には合わない場合もある
- ラヴェル「ソナチネ」ペルルミュテール版(Amazon)
- ラヴェル「ソナチネ」ペルルミュテール版(楽天市場)
比較表
| 版元 | 特徴・メリット | 解説の充実度 | 演奏指示 | 入手性 | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| デュラン版 | 原典重視・国際標準・日本語版あり | △ | × | ◎ | 上級者・指導者 |
| 音楽之友社版 | ペルルミュテール校訂・ヒント多 | ◎ | ◎ | ○ | 研究・参考用・指導者 |
ペルルミュテール版は、最高の校訂版…だと思っています。
ペルルミュテール版は最高の楽譜だけど、これしか見たことない…はもしかしたらデメリットになるかも?というのがデメリットかと思います。
ラヴェルのソナチネの名盤

ラヴェル《ソナチネ》は多くのピアニストによって録音されていて、名盤と呼ばれる演奏も多数存在します。以下、特に評価の高い録音や聴き比べで名盤とされるものを紹介です。
主な名盤ピアニストと特徴「まとめ表」
| ピアニスト | 特徴・評価 |
|---|---|
| アリシア・デ・ラローチャ | 上品で繊細、透明感と気品 |
| ヴァルター・ギーゼキング | 自然な流れ、全集も名盤 |
| マルタ・アルゲリッチ | ダイナミック、ライブ感 |
| モニク・アース | フランス的な繊細さ、コスパ良い全集 |
| アンヌ・ケフェレック | 伝統的なフランス・ピアニズム |
| クロード・エルフェ | 詩情豊かで温かみのある演奏 |
| オメロ・フランセシュ | 潤いときらめきのタッチ |
| 務川慧悟 | 現代日本の実力派、若い感性 |
| ルイ・ロルティ | 定番の全集、バランス良し |
| フランソワ・デュモン | 技術・表現ともに最高レベル |
初めて聴く方へのおすすめ
特に初めて《ソナチネ》を聴く方には、アリシア・デ・ラローチャ、ギーゼキング、ロルティ、務川慧悟の録音が広くおすすめされています。
まとめ:ラヴェルのソナチネ
ラヴェルの《ソナチネ》は、コンパクトな中にラヴェルらしさがギュッと詰まった名作です。
響きは繊細で美しく、構成は古典的で整っていて、聴くたびに新たな発見があるような作品です。
難易度としては中級者以上向けですが、第2楽章だけを弾くこともできますし、ステップアップの目標としてもぴったり。
楽譜は、原典に忠実なデュラン版と、演奏のヒントが豊富なペルルミュテール版のどちらかを選ぶのが良いと思います。
そして、名盤も本当に多く、いろんなピアニストの《ソナチネ》を聴き比べることで、自分のイメージがどんどん育っていくはず。
「いつか弾いてみたいな」と思っていた方も、「ちょっと難しそう…」と感じていた方も、ぜひ一度、触れてみてください。
ラヴェルのソナチネは、静かに、でも深く心に響く、そんな作品です。